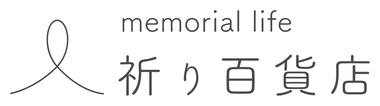「別れの季節」前編
父の静かな旅立ち
投稿日: 投稿者:祈り百貨店

第一章 家族との最後の瞬間
私は長女として、母と一緒に病院の白い病室に立っていた。冷たい空気が心を重くする。父が病床に横たわる姿が、あまりにも現実味がなくて、まるで夢の中にいるようだった。医師の告知が耳に響いた瞬間、私の心は凍りついた。「余命はわずかです」。その言葉は、まるで刃物のように私の胸を突き刺した。
父の顔は、病気にかかる前の力強い姿を失っていた。目の下には深いクマがあり、その表情はどこか安らぎを感じさせるものだった。母の手をしっかりと握りながら、私は父の横で静かに座っていた。母は、父の手を優しく撫でながら、「あなたがいてくれたから、私は幸せだった」と涙を流す。その言葉は、私の心に強く響いた。

思い出が次々と脳裏をよぎる。幼い頃、家族で過ごした楽しい日々が、まるでフィルムのように流れ出す。父が私たちを連れて行った海辺の旅行、妹と一緒に作った砂のお城、夜空に広がった星を見上げながらのキャンプ。どれもが温かく、心に残る瞬間だった。


私たちが父の側にいる時間が少なくなっていることを、心の奥底で感じていた。彼は、愛する家族に囲まれて静かに息を引き取る準備をしている。時折、私たちの顔を見て微笑むその姿は、どこか安堵の表情を浮かべているようだった。
病室の中は静寂に包まれていた。私たちの心臓の鼓動だけが聞こえる。やがて、父の息が次第に浅くなり、彼の目がゆっくりと閉じられていく。私たちはその瞬間を見守りながら、心の中で祈った。「どうか、痛みから解放されてください」と。

「ありがとう、パパ」と私は小さな声で呟いた。涙が頬を伝い、私の心の中で父への愛が溢れ出す。母もまた、心の底からの感謝を込めて「愛してるよ」と伝えた。父の息が静かになり、最後の瞬間、彼はかすかに微笑んだ。その顔を見たとき、私は父が今も私たちを見守っていると感じた。
病室を出ると、外の冷たい空気が私たちを迎え入れた。家族を失った悲しみが胸を締め付けるが、同時に父への愛が確かに存在していることを感じていた。これからの道のりは険しいが、母とともに父の思い出を大切にしながら歩んでいくことを、心に誓った。
私は長女として、家族を支え、父の遺してくれた愛を忘れないように努力する。家族の絆は、彼がいなくなっても決して消えることはない。私たちは、これからも父の思い出を胸に、共に歩んでいくのだ。

第二章 家族の思い出探し
葬儀社との打ち合わせが終わり、私たちはゆっくりと家に戻った。心の中には、悲しみと共に父の思い出が溢れていた。妹は私の横で静かに涙を拭いながら、何かを考えている様子だ。私たち姉妹は、父が愛したもの、そして彼が残してくれたものを振り返るために、アルバムを開くことにした。

家の中は静まり返り、時間がゆっくりと流れているように感じる。リビングのテーブルに座り、私たちはまず父と母の結婚式の写真が収められたアルバムを取り出した。母がそのページをめくると、若かりし頃の二人の笑顔が広がり、思わず息を呑んだ。「この時、パパは本当に幸せそうだったね」と、妹が言った。

私たちはそのまま、幼い頃の家族旅行の写真や、父が大好きだった海外旅行のアルバムにも手を伸ばした。ビーチでの楽しそうな姿、山登りでのはしゃいだ表情、そして私たちが小さい頃に行った動物園の写真が次々と出てくる。妹はその写真を見て、「この時、パパが笑っている顔が一番好き」と言った。私も同感だった。彼の笑顔は、私たちにとっての宝物だった。

夜は更け、私たちの思い出話は尽きることがなかった。父が好きだった音楽の話題になり、ビートルズの曲が流れる中、私たちは笑いながら歌った。父が私たちを車に乗せて、海へ向かう道中、いつも流れていた曲が、今では涙を誘うものになっていた。それでも、思い出を共有することで、彼の存在がより強く感じられた。

妹が、父の若かりし頃の写真を指さして、「この時のパパ、すごくイケてるね!」と笑った。その瞬間、私は思わず微笑んでしまった。私たち姉妹の会話は、父との思い出を通じて、心の奥深くにある愛を再確認する時間でもあった。
そして、ふと気付くと、私たちの手には、父が好きだった向日葵の種が握られていた。それは、母が庭で育てていたもので、父がいつも愛でていたものだった。「パパが好きだった向日葵、私たちも育てようよ」と妹が提案した。その言葉に私は心を打たれた。父の思い出を形にして、彼の愛を感じることができるのなら、私たち姉妹で一緒に育てていこうと決意した。

夜が深まる中、私たちは父の思い出をしっかりと抱きしめ、心の中にしまい込む。彼が残してくれた愛を、これからも大切に育てていくことを誓った。父は私たちに、思い出と共に生きる力を与えてくれたのだ。これからも、父との絆を感じながら、私たちは新しい一歩を踏み出していくのだろう。
シェア: