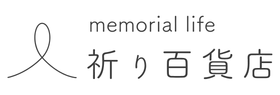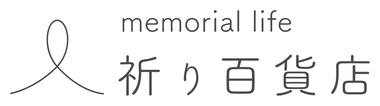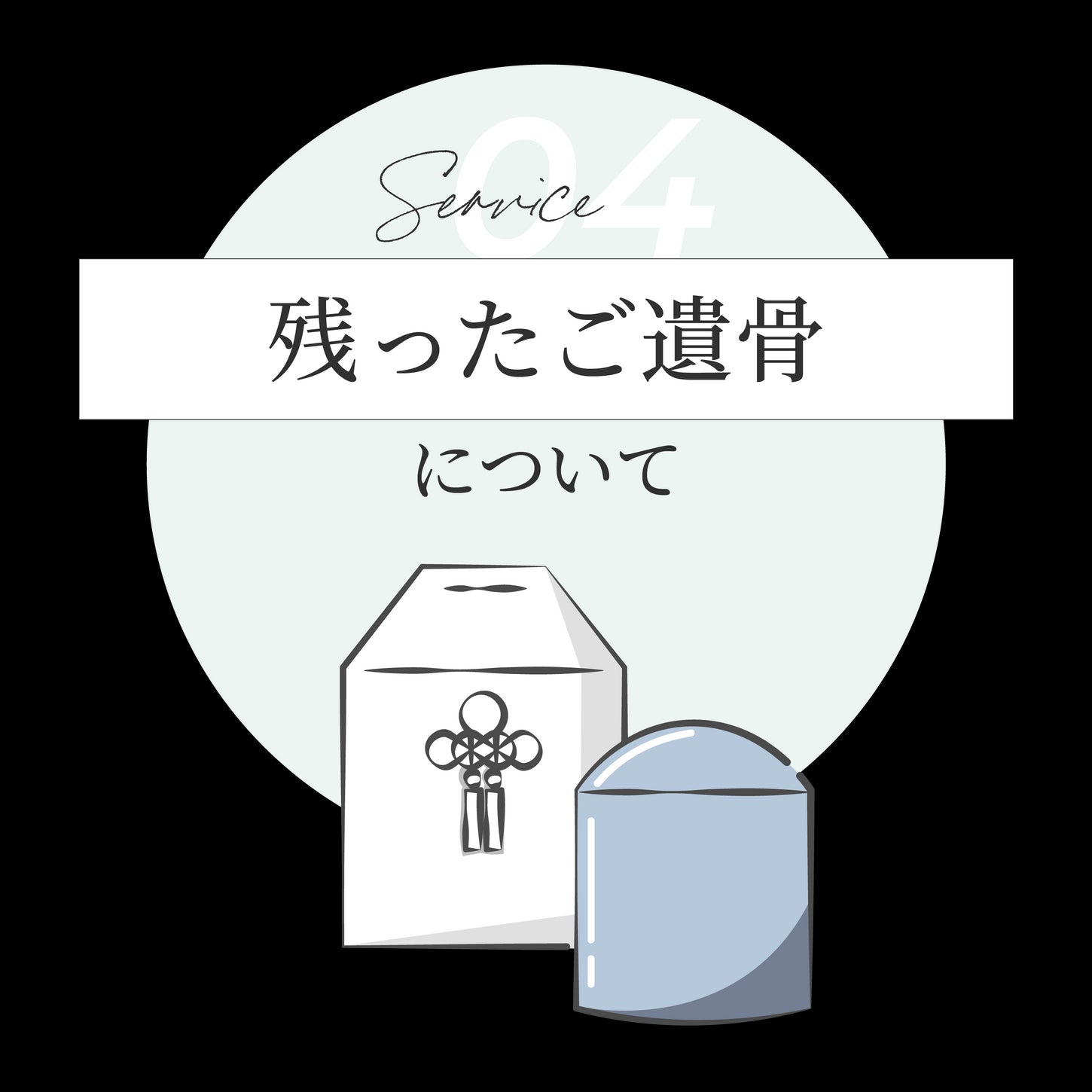よくある質問
Q & A
供養について
A.必ず用意しなければならないというものではありません。マンションなどにお住まいの場合、仏壇を置くスペースがないと言われる方もおられます。そのような方には手元供養をおすすめしていますが、ご先祖さまや故人さまをどのようなかたちで供養したいかを最優先で考えていただくのがいちばんです。
ちなみに、仏壇が登場するのは第40代天皇・天武天皇の頃です。天武天皇は仏教を手厚く保護し、国家仏教を推進した天皇ですが、その際、「寺院の本堂に模した仏舎をおのおので用意し、仏像や教典を置いてお祈りをするように」という勅令を出しました(686年)。この「仏舎」が後に仏壇になったと言われています。「日本」という国称を初めてお使いになったのも天武天皇です。
ちなみに、仏壇が登場するのは第40代天皇・天武天皇の頃です。天武天皇は仏教を手厚く保護し、国家仏教を推進した天皇ですが、その際、「寺院の本堂に模した仏舎をおのおので用意し、仏像や教典を置いてお祈りをするように」という勅令を出しました(686年)。この「仏舎」が後に仏壇になったと言われています。「日本」という国称を初めてお使いになったのも天武天皇です。
A.火葬を終えた遺骨は、四十九日法要に合わせてお墓に納骨するのが一般的ですが、お手元(ご自宅)に置いて供養されても構いません。遺骨の一部を分骨してご自宅に置き、手元供養をされる方も増えています。
A.遺骨はほとんどのご遺族がお墓に納骨しますが、中にはお墓が遠方にあってなかなか墓参りに行けないなどの理由から、納骨する分とは別に、遺骨の一部を手元(ご自宅)に置いて供養する方もおられます。 このように、遺骨を分けることを“分骨”と言います。また、ご両親の遺骨を兄弟姉妹がそれぞれ手元に置いておきたいというような場合や、子どもがいないなどの理由でお墓を維持できなくなり、いったんは納骨した遺骨を取り出して納骨堂に移すような場合も分骨になります(新しいお墓に遺骨を移す場合も分骨になります)。永代供養をお願いするような場合は、墓地や納骨堂の管理者に分骨する旨を記した書類(分骨証明書もしくは分骨用の火葬証明書)を提出する必要がありますが、手元供養のように遺骨を手元に置いておいても法律的に問題はなく、書類等を提出する必要はありません。 ただし、納骨前と納骨後の分骨とでは手続きが異なるので注意してください。
・納骨前に分骨証明書の発行を依頼するのは「火葬場」です。
・納骨後に分骨証明書の発行を依頼するのは「霊園・寺院の管理者」になります。
証明書はいずれも新しい分骨先(霊園・寺院)に提出しますが、納骨後に分骨する場合は、お墓を開ける必要があるので、どのようなやり方で遺骨を取り出すかについては、お墓の管理者と石材店にも相談してみてください。 分骨をする理由が、お墓を新しくする、あるいは墓じまいの場合は、仏壇と同じように、お墓も「閉眼供養」が必要になります。
・納骨前に分骨証明書の発行を依頼するのは「火葬場」です。
・納骨後に分骨証明書の発行を依頼するのは「霊園・寺院の管理者」になります。
証明書はいずれも新しい分骨先(霊園・寺院)に提出しますが、納骨後に分骨する場合は、お墓を開ける必要があるので、どのようなやり方で遺骨を取り出すかについては、お墓の管理者と石材店にも相談してみてください。 分骨をする理由が、お墓を新しくする、あるいは墓じまいの場合は、仏壇と同じように、お墓も「閉眼供養」が必要になります。
A.そのようなことはありません。四十九日を過ぎると故人さまは浄土して仏さまになるので、分骨したから成仏できないというようなことはありません。 また、分骨は「仏教の教えに反する」「縁起が悪い」とお考えの方もおられるようですが、それも誤りです。分骨は法律でも認められています。故人さまの遺骨を手元に置いて供養したいという方は、お気にされることなく、ご先祖さまと故人さまを供養なさってください。
A.手元供養をするための分骨であれば火葬後でも構いませんが、四十九日法要と納骨の際にあらかじめ用意した分骨用の骨壺にお分けになるのが望ましいかと思われます。
A.火葬後の遺骨を、ご遺族・ご親族が箸で拾って骨壺に納めることを「骨上げ(収骨)」と言います。最後に“喉仏※”を拾うのが一般的ですが、それは喉仏※のかたちが、仏さまが座禅を組んでいる姿に似ているので、大切な場所と考えられているからです。 喉仏※の骨を手元供養の骨壺に入れても何も問題はありませんが、遺骨はすべて故人さまの身体です。手元供養でどの部分の遺骨を納められても、そこにはかけがえのない故人さまの魂が宿っているとお考えいただきたいと思います。
※納骨時等に説明がある「喉仏」は背骨にあたる第二頚椎のことを指します。 一般的な「のど仏」にあたる部位は軟骨で火葬時に消滅します。
※納骨時等に説明がある「喉仏」は背骨にあたる第二頚椎のことを指します。 一般的な「のど仏」にあたる部位は軟骨で火葬時に消滅します。
A.はい、大丈夫です。しかし、人間の骨は有機物と無機物の複合体でできていて、カビはそのいずれにも生えるので、骨壺の保管場所や保存状態が悪いと、遺骨にカビが生える場合もあります。 湿度の高い場所や結露を起こしやすい状態での保管には気をつけてください。湿気防止のために、市販の乾燥剤を骨壺に入れられる方もおられます。
A. 必ずしも骨壷をご用意なさらなくても、故人さまの手元供養はできます。 ですが、手元供養はもともと、故人さまの遺骨を手元に置いて、供養したり祈りを捧げたりすることを指していました。 故人さまの遺骨を手元に置いておいても法的に問題はないので、「遺骨を自宅に置いても大丈夫なんだろうか」といったご心配もいりません。
A.仏壇を買い替えたり、お墓を新しくしたときに、魂を入れる儀式を「開眼法要(かいげんほうよう)」または「開眼供養」と言います。 もともとは仏像を彫ったとき、最後に目を入れて仏さまの魂をお迎えしていたのがはじまりです。同じように、仏壇も開眼法要をして仏さまの魂がこもるとされています。そのため、開眼法要は仏さまを迎え入れる“慶事”として執り行われます。「魂入れ」と呼ばれることもあります。 開眼法要をするには、僧侶に読経してもらいます。菩提寺の僧侶に来ていただくのが一般的ですが、近年では菩提寺をお持ちでなかったり、お寺とのおつきあいがなかったりする方もおられるので、そのような場合は葬儀社に紹介してもらうこともできます。また、インターネットで僧侶の派遣サービスも利用できます。 手元供養の場合、必ずしも開眼法要をする必要はありません。
※新しく買った仏壇は開眼法要をしますが、買い替え前の仏壇には「閉眼法要」をして魂を抜く必要があります。
※新しく買った仏壇は開眼法要をしますが、買い替え前の仏壇には「閉眼法要」をして魂を抜く必要があります。
A.新しい仏壇には「開眼法要」が必要ですが、その前に古い仏壇から“魂を抜く”必要があります。それを「閉眼法要」と言います。 開眼法要と同じように、菩提寺の僧侶に来ていただき、閉眼法要の読経をして古い魂から魂を抜き、新しい仏壇に魂を移します。 菩提寺をお持ちでなかったり、お寺とのおつきあいがなかったりする場合は、葬儀社に紹介してもらうか、インターネットで僧侶の派遣サービスを利用することができます。
A.神棚は神社を模して神さまを奉り、仏壇は寺院の本堂を模して仏さまを祀るので、それぞれは相反していますが、同じ部屋に神棚と仏壇があるのは、家族が一同に集いやすい、毎日のお参りをしやすいなどの理由から、むしろ“いいこと”とされています。 神棚は東向き(太陽が昇る方向)か南向き(陽がよく当たる方向)になるように置きます。仏壇は宗派による違いもありますが、神棚と同じ東向きか南向きがいいでしょう。できれば横並びにはしないほうがいいのですが、両方を並べる場合は、高さをそろえず、台を置くなどして、神棚が少し高くなるように配置します。神棚が向かって左側、仏壇を右側に置くことが多いです(逆でも問題ありません)。高さを少し変えれば、神棚と仏壇を並べても構いませんが、上下に配置するのはよくありません。これは、神さまと仏さまに優劣(上下関係)をつけることになるからと言われています。いずれも尊い存在なので、どちらが上で、どちらが下というようなことはありません。優劣をつけるようなことはしないようにしましょう。また、神棚と仏壇を向かい合わせに置くのは避けてください。向かい合わせにすると、神棚(神さま)に手を合わせているときには仏壇(仏さま)にお尻を向け、仏壇(仏さま)に手を合わせているときは神棚(神さま)にお尻を向けることになり、これはとても失礼なことになります。神棚と仏壇を向かい合わせに置くと、ご利益や霊験が逃げて、家庭内に厄をもたらすとも言われているので気をつけてください。お参りの順番は、神棚が先、仏壇が後とされています。
A. はい。位牌は、四十九日法要までと法要後では違います。 故人さまの戒名やお亡くなりになった年月日を記してお祀りする木札を「位牌」と言いますが、葬儀では「白木位牌」という全体が白い位牌(仮位牌)を祀り、四十九日法要を終えたら「本位牌」という位牌に替えます。 本位牌に故人さまの戒名(法名)を彫ったり、俗名(生前のお名前)を書き入れたりするのに時間がかかるので、四十九日法要に間に合うように、本位牌の準備をしておきましょう。 位牌には、故人さまの魂が戻ってくるとされています。戒名・俗名のどちらを入れても構いません。

A.はい。祈り百貨店では、位牌に戒名や没年月日などを彫れる「文字彫り」を承っております。戒名をお持ちでない場合は、俗名(生前のお名前)をお彫りします。お位牌の商品ページのオプションを選択しお申し込みいただくと、内容を確認後、こちらからメールでご連絡をさせていただきます。 仮のレイアウト図などのやり取りでご確認していただき、お客様のOKが出ましたら、制作開始いたします。制作開始より10日〜2週間ほどで戒名を入れた位牌をお届けいたします。 文字彫りを追加しても、しなくても料金は変わりません。詳しくは「サービス2 お位牌文字彫りサービス」のページをご覧ください。
A.手元供養で位牌を置かれる場合は、必ずしも開眼法要をする必要はありません。位牌は、故人さまやご先祖さまが一時的に宿る「依代(よりしろ)」とされており、その魂を迎え入れる儀式が、位牌の開眼法要です。開眼法要を経た位牌は、故人さまが宿る目印となると考えられています。仏壇の開眼法要と同じように、菩提寺の僧侶に読経していただき、位牌に故人さまの魂を迎え入れます。また、位牌を新しくするときも“魂抜き(閉眼法要)”をしてから、新しい位牌の開眼法要に移ります。
A.りんは、読経の際に僧侶が叩いて鳴らす「梵音具(ぼんおんぐ)」という仏具です。一般家庭でも使われる仏具ですが、りんの涼やかな音色には、邪気を払い、供養する人の心を清める働きがあると言われています。 りんの音色は故人さまにも届くと言われているので、手元供養をされる際には用意しておきたいお道具のひとつになります。りんの内側を叩く宗派もありますが、特に決まりはありません。りんは二回鳴らし、二回目を少し強めに鳴らします。
A.ご先祖さまや故人さまに手を合わせたら、心の中でお経を唱えなさいという宗派もありますが、手元供養には「こうでなければならない」という定義や決まりはありません。 “故人供養”と言い換えることもできるので、故人さまがおられるところが穏やかな世界であるように祈ったり、供養される方の近況を報告したりするなど、故人さまとの会話をする場と考えていただくのがよろしいかと思います。 「お早う」「お休み」「行ってきます」「ただいま」と毎日の挨拶をするように、故人さまとの会話が日常に溶け込むと、故人さまとの絆や心の距離は、より近くに感じられるようになるのではないでしょうか。
A.仏壇に祀る仏具を「具足」と言います。 従来の仏壇では具足を五つ用意するので「五具足」と言いますが、手元供養では「花立」「香炉」「火立(ひたて)」の三つを用意すれば問題ないとされています。その三種類の具足を総じて「三具足(みつぐそく)」と言います。
A.「花立」は、供花(お供え花)を飾る花瓶です。故人さまがおられるところが美しい世界であるようにと願いを込めて花を手向けますが、雨風に堪え忍んで咲く草花は、厳しい修行に耐える仏教の教えにも通じるところがあるため、仏壇にも供花を供えるようになりました。 もともとお墓や仏壇には、菊などの「仏花」を供えていましたが、近年ではドライフラワーやプリザーブドフラワーのような華やかな花を飾る方も多くなりました。
「香炉」は、線香を焚く際に使う仏具です。「前香炉」と呼ばれる仏具が一般的ですが、線香が倒れないように、中に香炉灰(わら灰)を敷いて線香を焚きます。香炉灰を使うと、風で灰が舞い散ったり、香炉をうっかり倒したりしたときに灰がこぼれて仏壇周りが汚れることがあるため、灰の代わりに「香炉石」をご利用になる方も増えています。 香炉石は、チップ状に粉砕した天然石を使っているので、わら灰のようにこぼれる心配もなく、見た目も鮮やかで、水洗いをすれば繰り返し使えるので手入れも簡単です。 香炉には線香をあげるのが一般的ですが、香りの供養は、香りで場や人々の心を清めるという意味があり、火を使いたくない時は、アロマオイルを使うのもおすすめです。
「火立」というのは、ロウソクを立てる燭台のことです。ロウソクの炎を“灯明(とうみょう)”と言い、この炎が人の心に明かりを灯し、お盆などに故人さまがお帰りになる際の道しるべにもなると考えられています。そのため、供養には欠かせないお供え物のひとつになっています。 火立てに立てたロウソクの火で線香を焚く方もおられますが、線香を焚く際は、マッチかライターなどの火器をお使いになるようにしてください。また、ロウソクを消すときも息を吹きかけて消さないようにしましょう。
手元供養では、場所を取らないコンパクトサイズのミニ仏壇をご利用されることが多いと思います。五具足の場合はそれぞれ置き場所が決められていますが、手元供養で祀る三具足は、置き場所もおのおのが自由に配置していただいて構いません。故人さまに喜んでもらえるようなレイアウトを考えていただくのがいちばんです。
「香炉」は、線香を焚く際に使う仏具です。「前香炉」と呼ばれる仏具が一般的ですが、線香が倒れないように、中に香炉灰(わら灰)を敷いて線香を焚きます。香炉灰を使うと、風で灰が舞い散ったり、香炉をうっかり倒したりしたときに灰がこぼれて仏壇周りが汚れることがあるため、灰の代わりに「香炉石」をご利用になる方も増えています。 香炉石は、チップ状に粉砕した天然石を使っているので、わら灰のようにこぼれる心配もなく、見た目も鮮やかで、水洗いをすれば繰り返し使えるので手入れも簡単です。 香炉には線香をあげるのが一般的ですが、香りの供養は、香りで場や人々の心を清めるという意味があり、火を使いたくない時は、アロマオイルを使うのもおすすめです。
「火立」というのは、ロウソクを立てる燭台のことです。ロウソクの炎を“灯明(とうみょう)”と言い、この炎が人の心に明かりを灯し、お盆などに故人さまがお帰りになる際の道しるべにもなると考えられています。そのため、供養には欠かせないお供え物のひとつになっています。 火立てに立てたロウソクの火で線香を焚く方もおられますが、線香を焚く際は、マッチかライターなどの火器をお使いになるようにしてください。また、ロウソクを消すときも息を吹きかけて消さないようにしましょう。
手元供養では、場所を取らないコンパクトサイズのミニ仏壇をご利用されることが多いと思います。五具足の場合はそれぞれ置き場所が決められていますが、手元供養で祀る三具足は、置き場所もおのおのが自由に配置していただいて構いません。故人さまに喜んでもらえるようなレイアウトを考えていただくのがいちばんです。
A.必ずしも用意する必要はありません。もともと陰膳は、遠方に住んでいたり、長期の旅行や戦地に出征していたりして、なかなか会えないご家族の無事を祈って用意していた食事でした。現在では、故人さまが極楽浄土に無事に到着されるようにとの願いを込めて用意する食事を言うようになりました。 そのため、故人さまが極楽浄土に向かわれる四十九日法要までを陰膳と言い、それ以降は仏さまへの“お供え”になります。陰膳は、一汁三菜などの精進料理や、野菜、煮物などの家庭料理を“仏膳椀(ぶつぜんわん)”という食器に盛り、おさがりは捨てずに、家族でいただいていました。それも供養のひとつでした。 本来の陰膳は、仏膳椀の置き場所も決められていますが、手元供養では、陰膳そのものを用意しなくてもいいと考えられています。菓子折などの頂き物があったときに、故人さまにも「おひとつどうぞ」と供えたり、故人さまがお好きだった食べ物やお菓子、お酒やコーヒーなどをたしなまれる方であれば、そうした嗜好品をときおりお供えすれば良いのではないでしょうか。
※浄土真宗のように、最初から陰膳を用意しない宗派もあります。
※浄土真宗のように、最初から陰膳を用意しない宗派もあります。
A.大丈夫です。従来の仏壇であれば、宗派によっては、ペットを仏壇に祀ってはいけないという考えもありますが、「祈り百貨店」は、手元供養でお使いになる仏壇は“供養壇”と考えているので、むしろ自由に弔いをしていただきたいと思っております。 たとえば、故人さまが可愛がっていたペットも旅立ったとき、ペットが着けていた首輪などを故人さまの写真と一緒に飾って供養したら、故人さまも喜んでくださるのではないでしょうか。
A.基本的には問題ありません。 実際、ご主人さまと奥さまのご実家の宗派が異なるため、それぞれの宗派に合わせた仏壇を置いている方もおられないわけではありません。そのような場合は、仏壇を置く部屋を別にしたり、供養に偏りがないように、双方とも均等にお参りをして、供物をお供えしたりする必要があります。 どうしても同じ部屋に祀らなければならないときは、向かい合わせにならないように配置します。これは、片方の仏壇に手を合わせているとき、もうひとつの仏壇にお尻を向けることになり、仏さまに対して失礼になるからです。 しかし、できるならば、仏壇はひとつにまとめたほうがいいかもしれません。日本の慣習では、ご主人さまの仏壇にするのが一般的ですが、他宗派の仏壇と一緒にしていいかどうかは菩提寺の住職に相談してみましょう。ひとつにまとめるのを住職が望まなければ、仏壇は二つのままでも構いません。 これはご夫婦双方のご先祖さまや故人さまの供養につながる大切な問題なので、ご夫婦でよく話し合い、ご親族や住職の意見を聞いて、慎重に判断なさってください。
A.従来の仏壇に敷く敷物は、正しくは「打敷(うちしき)」と言います。ふだんは敷きませんが、法事やお盆、お彼岸などの特別な日や祭事のときに使います。打敷は夏と冬で使い分けたり、サイズや、打敷を飾る場所なども宗派によって異なります。 千円から数千円で買えるお手頃価格の打敷もありますが、絹でできていたり、刺繍を施していたり、中には西陣織の打敷など、絢爛豪華で高価な打敷もあります。 手元供養の場合は、打敷にこだわる必要はないと思われます。ご先祖さまや故人さまをしのび、祈りを捧げる大切な場所に彩りを添える感じで、故人さまが喜んでくださるような、可愛い打敷や、華やかな打敷など、インテリア感覚で敷物をご用意いただくといいように思います。 従来の仏壇と手元供養のどちらにも言えるのは、打敷は故人さまの魂が宿る仏壇を飾る仏具のひとつなので、常に清潔な状態で敷くようにすることです。
A. お供え花は故人さまにたむける花です。できるだけ飾ったほうがいいでしょう。 葬儀や墓前に花を手向けるのは、洋の東西を問わず、亡くなった方の冥福を祈る行為で、古来から伝わる慣習のひとつです。「故人さまがおられるところが花が咲き誇るような美しい場所であるように」との願いを込めて花を飾ります。 また、雨風に堪え忍んで咲く草花は、厳しい修行に耐える仏教の教えにも通じるところがあるため、仏壇にもお供え花を飾るようになったとも言われています。 四十九日法要までは白い花をたむけることが多く、四十九日法要以降は淡い色合いの花をたむけるのが一般的ですが、手元供養の場合は、特に色彩にこだわる必要はありません。 子どもの成長を祝う「七五参」の、「七・五・三」という数字にも実は意味があって、たとえば庭木に植える植物も、縁起のいい松・竹・梅や南天、センリョウやマンリョウなどから三種類選び、それぞれ七本、五本、三本でそろえるといいとされています。 それと同じように、仏壇に飾るお供え花も、三色か五色の組み合わせがいいと言われていますが、近年ではドライフラワーやプリザーブドフラワーのような華やかな花を飾る方も多くなりました。 どのような花を飾るかは自由ですが、バラやアザミのようにトゲのある花や、ヒガンバナやシャクナゲなど、毒を含む花は飾らないようにしましょう。また、生花を飾る場合、椿や山茶花(さざんか)など、散るのが早い植物も避けるようにします。
A.黒でなくても大丈夫です。 故人さまの生前のお姿を写した写真を「遺影」と言います。必ずしも用意しなくてもいいとされていますが、故人さまをしのんで飾られる方は多くおられます。 遺影にどのような写真をお選びになるかも自由です。かしこまって写した写真ではなく、笑っておられたり、帽子をかぶっている写真でも構いません。ご遺族の方がご覧になって、いちばん故人さまらしい一枚をお選びください。 A4サイズの遺影は、専用の額縁に入れて、和室の鴨居(かもい)部分などに飾ることが多いですが、手元供養の場合、卓上サイズの写真立てのほうがすっきりすると思います。遺影なのでフレーム(額縁)は黒のイメージですが、黒でなければならないという決まりもなく、最近はさまざまな色合いのフレームが選ばれています。 また、遺影は写真だけでなく、肖像画でもいいとされています。