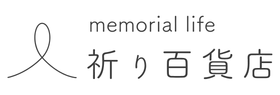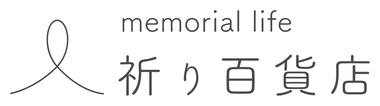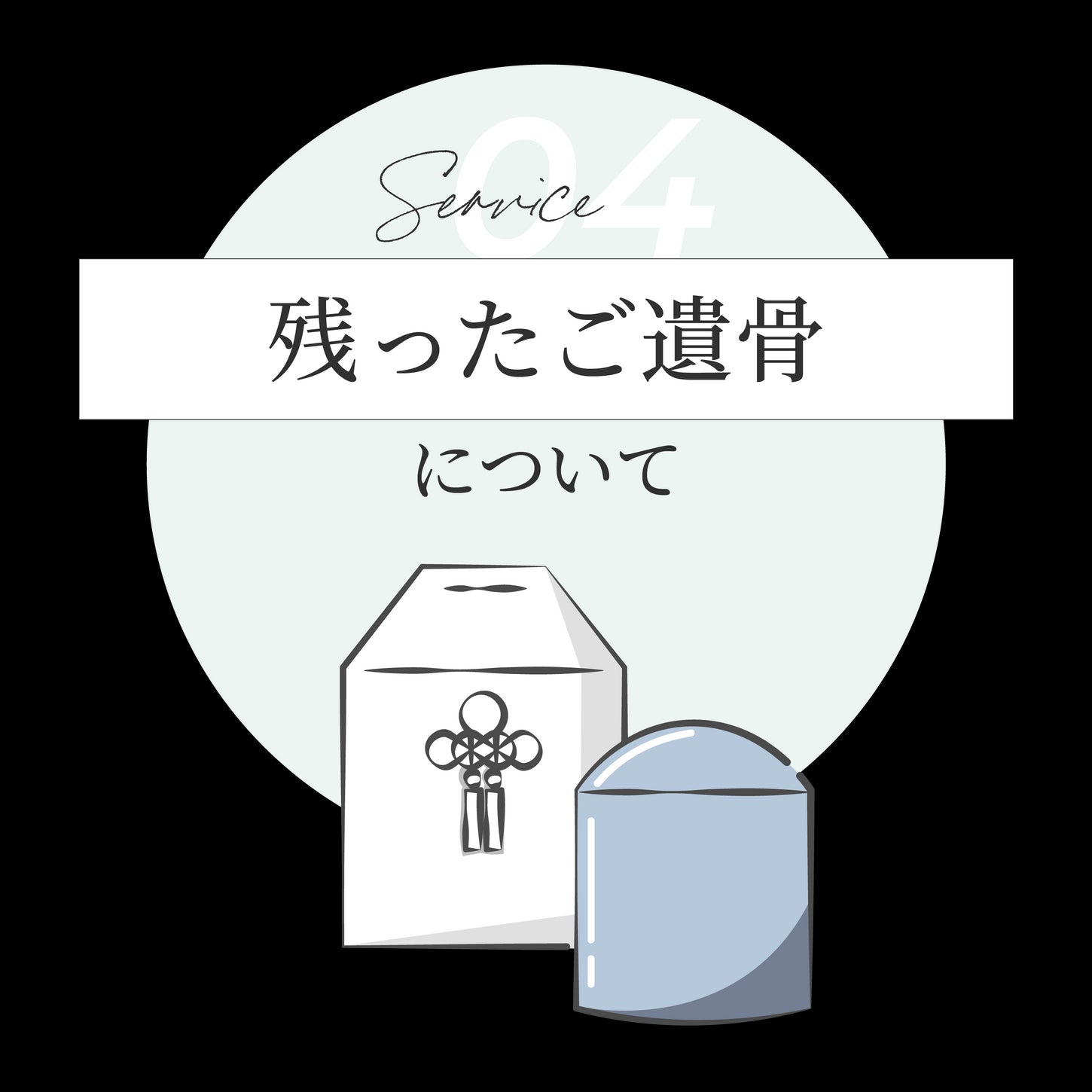暮らしの多様化にともない、
供養に関するさまざまなお悩みの声が増えています。
“手元供養”は、形式にとらわれず、
リビングなど身近な場所で
故人をそっと偲ぶ、新しい供養のかたち。
大切な想いをそのままに、
あなたの暮らしに寄り添う
供養のかたちを見つけてみませんか。












- 手元供養に関するミニコラム
- そもそも手元供養って?



手元供養とは、遺骨を全部あるいは一部を自宅など身近な場所で保管し、故人さまを身近で供養する祈りのかたちです。仏壇は別にあり分骨で供養したい方や、お墓を持つ必要がない、従来の仏壇を置くスペースがない方など、生活スタイルや住環境も変化する中、広がった新しい供養のスタイルです。
必要な道具の選び方
手元供養には明確な決まりごとはありません。お住まいの中に“癒し”や“祈り”の場をつくるため、当店ではさまざまな供養品をご用意しています。以下はラインナップの一例です。お好きなものを組み合わせたり、スペースに合わせて一部だけを選んだり——ご自宅に合うスタイルを自由にお探しください。


- 「ステージ」を選ぶ
- マンション住まいで仏壇を置くスペースがないようなときは、コンパクトなデザインで場所を取らない小さな仏壇をリビングルームや寝室などに置いていただいて、故人さまを供養することができます。その仏壇を総じて「ステージ」と呼んでいます。

- 「ミニ骨壷」を選ぶ
- 火葬した故人さまの遺骨を納める壺を「骨壺」と言います。四十九日法要に合わせて納骨するのが一般的ですが、具体的な期日は定められていません。また、必ず納骨しなければならないという決まりもないので、遺骨を自宅に置かれる方も増えています。

- 「お位牌」を選ぶ
- 故人さまの戒名やお亡くなりになった年月日を記してお祀りする木札を「位牌」と言います。この位牌に故人さまの魂が戻ってくるとされています。俗名(故人さまの生前のお名前)を入れても構いませんが、魂入れと呼ばれる「開眼供養」が必要です。

- 「三具足」を選ぶ
- 仏壇に祀る3種類の仏具を総じて「三具足」と言います。線香を焚く「香炉」、ロウソクを立てる「燭台(火立)」、仏花を飾る「花立」の三つです。従来の仏壇では「五具足」が基本になりますが、手元供養では三具足で問題ないとされています。

- 「りん」を選ぶ
- 読経や供養の際に鳴らす仏具を「りん」と言います。りんの涼やかな音色が邪気を払い、供養する人の心を清めると言われています。りんの内側を叩く宗派もありますが、特に決まりはありません。りんは二回鳴らし、二回目を少し強めに鳴らします。

- 「敷物」を選ぶ
- ステージの下に敷いて、場を華やかに演出したり、供養の場として仏具を上に飾って、祈りのスペースを区切ることができます。季節によって、素材や柄、色味を変えてもよいでしょう。

- 「お花」を選ぶ
- 仏壇に飾る花を「仏花」と言います。どのような花を飾るかは自由ですが、バラやアザミのようにトゲのある花や、ヒガンバナやシャクナゲなど、毒を含む花は飾らないようにしましょう。近年では造花やプリザーブドフラワーを飾る方も増えています。

- 「フォトフレーム」を選ぶ
- 故人さまの生前のお姿を写した写真を「遺影」と言います。必ずしも用意しなくてもいいとされていますが、故人さまをしのんで飾られる方は多くおられます。遺影なのでフレームは黒のイメージですが、さまざまな色合いのフレームが選ばれています。