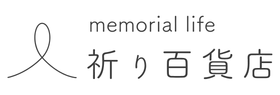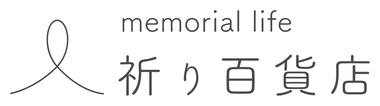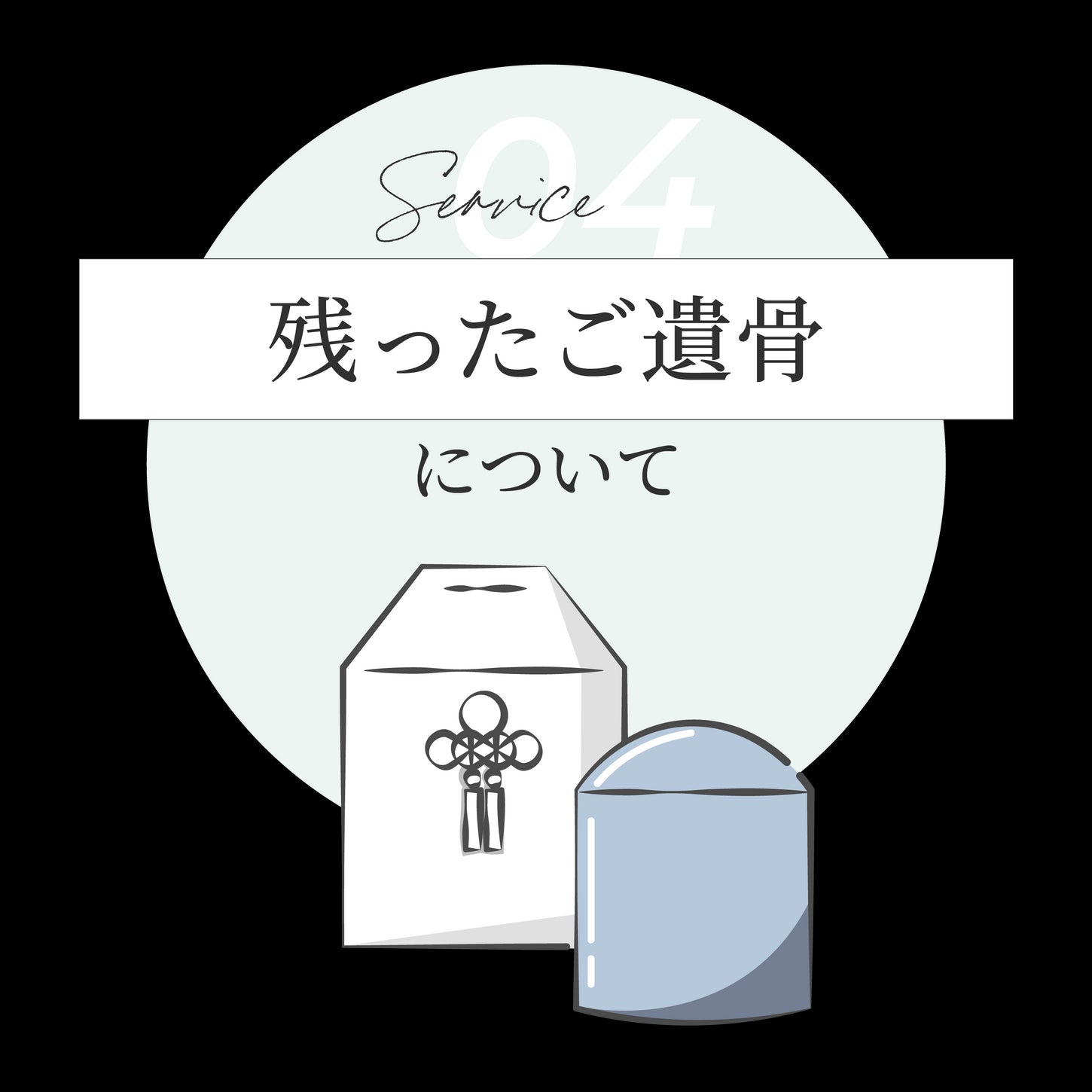分骨の手続きとミニ骨壷 〜手元供養のために知っておきたいこと〜
投稿日: 投稿者:祈り百貨店

分骨とは、故人の遺骨を複数の場所に分けて安置することを指します。この行為は、古くから日本の仏教文化に根付いた慣習であり、 現代においても多くの人々に選ばれています。分骨の背景や目的、手続き、そして手元供養との関連について詳しく解説していきましょう。
- 目次
- 分骨とは何ですか。
- 分骨の背景
- 分骨の目的
- 分骨の注意点
- 手元供養との関連
- 分骨の手続き
- 分骨のタイミングは? 火葬したらすぐに分骨してもいいのですか?
- 喉仏の骨を手元供養の骨壺に入れてもいいでしょうか?
- 遺骨はそのまま骨壺に入れて大丈夫? カビが生えたりしない?
- 分骨するためのミニ骨壷の素材はどんなものがある? それぞれの特徴は?
- 結論
分骨とは何ですか。
遺骨はほとんどのご遺族がお墓に納骨しますが、中にはお墓が遠方にあってなかなか墓参りに行けないなどの理由から、納骨する分とは別に、遺骨の一部を手元(ご自宅)に置いて供養する方もおられます。このように、遺骨を分けることを“分骨”と言います。
また、ご両親の遺骨を兄弟姉妹がそれぞれ手元に置いておきたいというような場合や、子どもがいないなどの理由でお墓を維持できなくなり、いったんは納骨した遺骨を取り出して納骨堂に移すような場合も分骨になります(新しいお墓に遺骨を移す場合も分骨になります)。
分骨の背景
分骨は、日本独特の葬送文化の一部として位置づけられます。伝統的に、日本においては故人を一か所に埋葬することが一般的でしたが、近年では家族構成やライフスタイルの変化に伴い、分骨を選ぶケースが増加しています。特に、都市部に住む家族が地方にある故人の墓にアクセスしづらい場合や、故人が生前に特別な思いを寄せていた場所に遺骨を分けたいという願いが強くなっています。
また、分骨は、故人を身近に感じることができる方法としても注目されています。故人が愛した場所や、家族が集まる場所に遺骨を安置することで、日常生活の中で故人とのつながりを感じることができるのです。例えば、故人の趣味や好みに合わせた場所に遺骨を分けることで、故人の思い出を共有し続けることができます。
分骨の目的
分骨の目的は、さまざまです。まず第一に、故人の遺志を尊重することが挙げられます。故人が生前に特定の場所に埋葬されることを望んでいた場合、その意向に沿った形で分骨を行うことが大切です。また、家族や親族がそれぞれの生活環境や事情を考慮し、故人を身近に感じられる形で供養を行うことも重要です。
さらに、分骨は、家族間でのコミュニケーションを深める機会にもなります。遺族が集まり、どのように分骨を行うか話し合うことで、故人に対する思いを共有し、家族の絆を再確認することができます。特に、離れて住んでいる家族がいる場合、分骨を通じて一堂に会する機会を持つことができるのです。
分骨の注意点
分骨を行う際には、いくつかの注意点があります。まず最初に、遺族全員の合意を得ることが重要です。分骨は、故人の遺志を尊重するだけでなく、残された家族が納得できる形で行われるべきです。したがって、分骨の方法や場所について家族全員で話し合い、意見を尊重し合うことが求められます。
次に、分骨を行うためには、通常、遺骨を管理している寺院や霊園、火葬場からの許可が必要です。これは、故人の遺骨を適切に扱うための法的な手続きとして重要です。多くの場合、分骨証明書という書類が発行され、これをもとに遺骨を移動させることができます。この証明書は、遺骨を分ける際の重要な書類であるため、しっかりと保管しておくことが大切です。
また、分骨を行う際には、遺骨を丁寧に扱うことが求められます。遺骨は、故人の大切な一部であり、扱いには細心の注意を払う必要があります。分骨を行う際には、遺骨を安置する場所を清め、その場所が故人にふさわしいものであることを確認してください。
手元供養との関連
分骨と手元供養は、密接に関連しています。手元供養とは、故人の遺骨の一部を自宅で供養することを指します。この方法は、故人を身近に感じ、日常生活の中で思いを寄せるための手段として広がっています。手元供養には、ミニ骨壷やペンダント型の遺骨入れなどが用いられ、これらはインテリアとしても違和感なく置けるようなデザインが多く、現代のライフスタイルにフィットしています。
手元供養を行うことで、故人とのつながりをより深く感じることができます。特に、忙しい現代人にとって、日常の中で故人を思い出す時間を持つことは、心の安定や癒しにつながることもあります。また、手元供養は、家族での供養の形を選ぶ自由度が高く、個々のライフスタイルに合わせた方法を選択できる点も魅力です。
分骨の手続き
分骨を行う際の手続きについても触れておきましょう。まず、遺族の代表者が分骨を希望する旨を葬儀社や寺院に伝えます。次に、必要に応じて分骨証明書を取得し、分骨を行う場所を決定します。分骨を行う際には、丁寧に遺骨を扱い、新しい安置場所にふさわしい供養を行うことが大切です。
実際の手続きは、以下のような流れで進むことが一般的です。
1.遺族の合意
まず、遺族全員で分骨について話し合い、合意を得ます。
2.寺院や霊園への相談
分骨を希望する旨を寺院や霊園に伝え、必要な手続きを確認します。
3.分骨証明書の取得
分骨に必要な書類を準備し、分骨証明書を取得します。
4.分骨の実施
遺骨を丁寧に扱い、指定された場所へ分骨を行います。
5.供養の実施
分骨後、遺骨を安置した場所で供養を行います。
これらの手続きを通じて、故人への最後の感謝の気持ちを伝えることができるのです。
手元供養のように遺骨を手元に置いておいても法律的に問題はなく、書類等を提出する必要はないと言われていますが、
お墓に戻したり、永代供養や散骨等をお願いするような場合は、墓地や納骨堂の管理者に分骨する旨を記した書類
(分骨証明書もしくは分骨用の火葬証明書)を提出する必要があります。
ただし、納骨前と納骨後の分骨とでは手続きが異なるので注意してください。
Point!
- 納骨前に分骨証明書の発行を依頼するのは「火葬場」です。
- 納骨後に分骨証明書の発行を依頼するのは「霊園・寺院の管理者」になります。
分骨のタイミングは? 火葬したらすぐに分骨してもいいのですか?
手元供養をするための分骨であれば火葬後でも構いませんが、四十九日法要と納骨の際にあらかじめ用意した分骨用の骨壺にお分けになるのが望ましいかと思われます。

喉仏の骨を手元供養の骨壺に入れてもいいでしょうか?
火葬後の遺骨を、ご遺族・ご親族が箸で拾って骨壺に納めることを「骨上げ(収骨)」と言います。最後に“喉仏※”を拾うのが一般的ですが、それは喉仏※のかたちが、仏さまが座禅を組んでいる姿に似ているので、大切な場所と考えられているからです。 喉仏※の骨を手元供養の骨壺に入れても何も問題はありませんが、遺骨はすべて故人さまの身体です。手元供養でどの部分の遺骨を納められても、そこにはかけがえのない故人さまの魂が宿っているとお考えいただきたいと思います。 ※納骨時等に説明がある「喉仏」は背骨にあたる第二頚椎のことを指します。 一般的な「のど仏」にあたる部位は軟骨で火葬時に消滅します。
遺骨はそのまま骨壺に入れて大丈夫? カビが生えたりしない?
はい、大丈夫です。しかし、人間の骨は有機物と無機物の複合体でできていて、カビはそのいずれにも生えるので、骨壺の保管場所や保存状態が悪いと、遺骨にカビが生える場合もあります。 湿度の高い場所や結露を起こしやすい状態での保管には気をつけてください。湿気防止のために、市販の乾燥剤を骨壺に入れられる方もおられます。
分骨に使うミニ骨壷の素材はどんなものがある? それぞれの特徴は?
遺骨を入れる骨壷も様々な素材があります。一般的な素材とその特徴を以下にまとめました。
陶器(焼き物)
陶器は比較的耐久性があり、長期間使用することができます。彩色や模様の選択肢が豊富で、個性的なデザインが可能です。
木材
木製の骨壷は、手にしたときの温もりのある素材感や、自然の風合いが特徴です。また、インテリアと調和しやすい素材と言えるでしょう。
金属
金属は非常に耐久性があり、長期間使用することができます。しっかり閉まるので密閉性もあります。ステンレス鋼や真鍮などの金属製骨壷は、高級感があり、スタイリッシュな印象です。
ガラス
ガラス製のミニ骨壷は、繊細な彫刻や模様、色彩などのデザイン性が特徴です。透明感があり、内部や装飾が見えるデザインを施したり、美しい光沢感も特徴として挙げられます。ただし、割れやすい性質があるため、注意深く取り扱う必要があります。
石材
石材の骨壷は非常に堅牢で耐久性があります。重厚感があり、特別な存在感を持ちます。

終わりに
分骨は、故人をさまざまな形で偲ぶための一つの方法であり、家族の事情や故人の遺志を大切にしながら、最適な供養の形を選ぶことが何よりも重要です。分骨や手元供養を通じて、故人との思い出をいつまでも大切にし、心の中で生き続けることができるのです。分骨のプロセスは、家族間のコミュニケーションを深める機会にもなり、故人とのつながりを感じる大切な時間となるでしょう。
故人を偲ぶ思いを大切にしながら、適切な供養の形を見つけていきたいものですね。分骨や手元供養を通じて、故人との絆をより深めていくことができることを願っています。
祈り百貨店でも、自然の風合いを活かした木の骨壷や、伝統技法を用いた、美しい模様、日本製の素材にこだわったミニ骨壷など各種取り揃えております。ぜひ商品情報もご覧ください。
シェア: