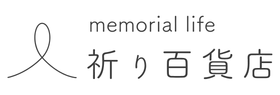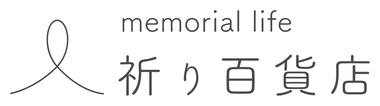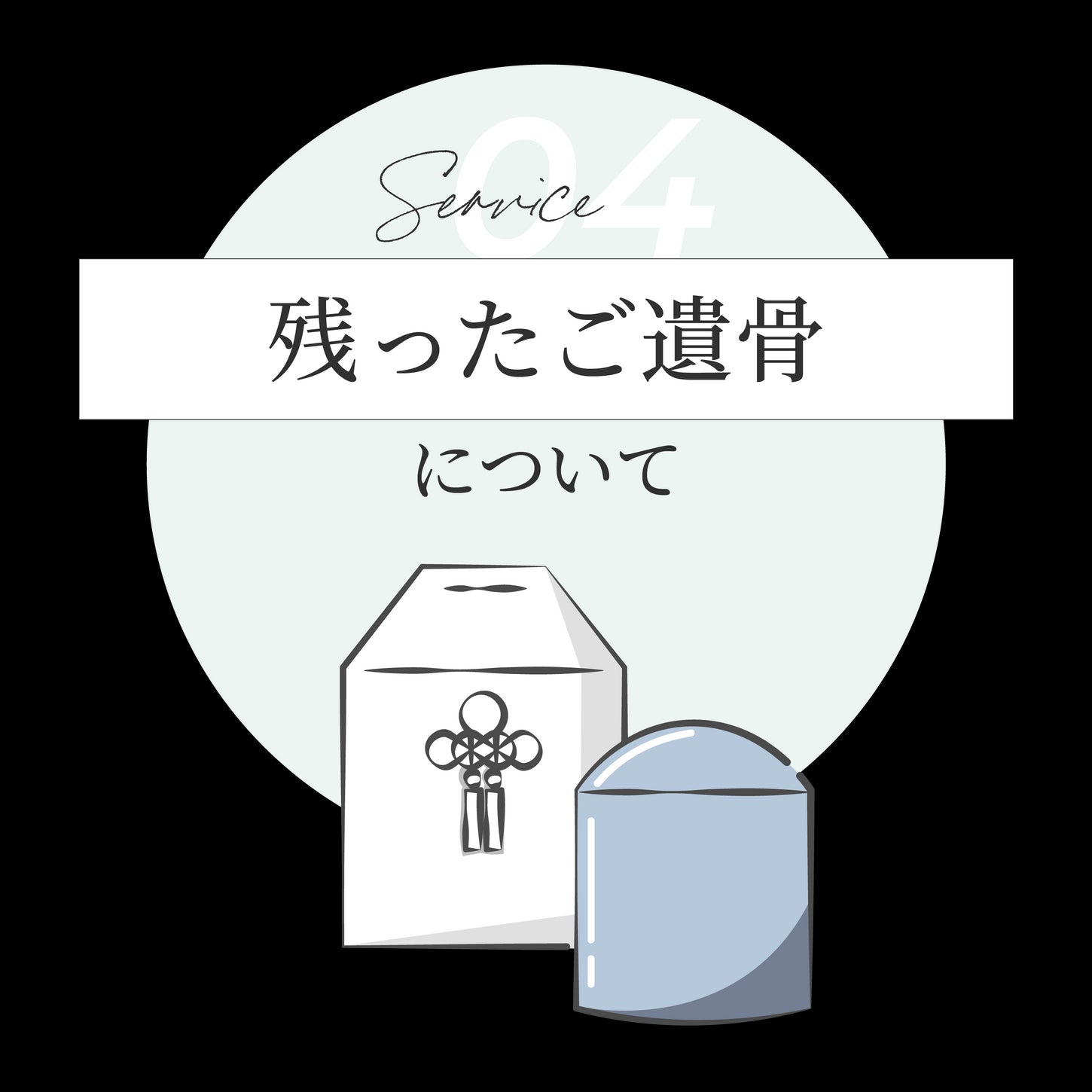女性のためのお葬式講座 ① 喪主編 事前相談の重要性
投稿日: 投稿者:祈り百貨店

お葬式の準備は、心の整理をするためにも非常に重要です。特に喪主としての役割を担う場合、事前にしっかりと話し合っておくことで、スムーズに進めることができます。ここでは、お葬式に関する基本的なポイントを詳しく解説し、何を決めなければならないのかを整理しました。
1. 事前又は事後早々に相談して決めること
事前に決めておくべき事項は多岐にわたります。これらを把握しておくことで、葬儀の流れがスムーズになり、心の負担も軽減されます。

1.看取りの場所
故人がどこで看取られるかは非常に重要な選択です。施設(介護ホーム)、自宅、または病院のいずれかを選ぶことができます。自宅での看取りは、故人が愛する空間で最後の時を過ごせるという意味で心温まる選択ですが、看護や介護の体制を整える必要があります。一方、病院や施設での看取りは、専門的なケアを受けられる利点があります。この選択を行う際には、故人の意向や家族の状況を考慮することが大切です。
2.安置場所
看取った後、故人の遺体をどこに安置するのかを決める必要があります。自宅での安置が可能な場合もありますが、葬儀社の提案する安置所を利用することも一般的です。安置場所は、葬儀までの準備を行うための重要な場所であり、故人を偲ぶための空間ともなりますので、静かで落ち着いた環境を選ぶことが望ましいです。
3.搬送業者
故人を搬送する際には、どの業者に依頼するかも重要なポイントです。搬送のみを行う業者か、葬儀社に包括的に任せるかの選択肢があります。葬儀社に依頼する場合、搬送と葬儀の手配が一括で行えるため、スムーズです。また、搬送中に故人を大切に扱ってもらえるかどうかも、業者選びの重要な要素です。
4.葬儀社
葬儀社は葬儀全体の流れをサポートしてくれる存在です。事前に葬儀社を決めておくことで、安置場所や搬送業者の手配もスムーズに行えます。葬儀社選びでは、費用やサービス内容、自社式場の有無、近隣の公共式場の紹介などを確認し、自分たちのニーズに合った業者を選ぶことが大切です。信頼できる葬儀社の存在は、葬儀後の心の安定にも寄与します。
5.火葬場
式場からのアクセスや、最寄りの火葬場の有無を事前に確認しておくことも重要です。火葬場の予約も必要となるため、葬儀社と連携を取りながら、スムーズに手続きを進めることが求められます。
6.葬儀スタイル
葬儀のスタイルを決定することも、事前に考えておくべきことの一つです。仏式、無宗教、キリスト教式など、故人の宗教観や家族の意向に応じたスタイルを選びます。また、葬儀の形式(通夜、告別式、火葬など)も考慮に入れ、どのような流れで行いたいかを決めます。
7.葬儀の規模
参加者の人数を想定し、葬儀の規模を決めることも大切です。多くの人を招く場合は、式場の広さや設備も考慮する必要があります。また、会葬者に配慮した準備(椅子や立食のスペース、飲食物の用意など)も必要です。
2.細かなことの打ち合わせ
基本的な事項が決まった後は、葬儀社と具体的な打ち合わせを行います。この段階では、詳細な流れに沿って、必要な手続きを進めていきます。

8.宗教者への手配
葬儀において宗教者が必要な場合は、その手配を行います。宗教者のスケジュールを確認し、通夜の有無や、特に仏式の場合は初七日法要の計画を立てることが重要です。 また宗教者へのお布施や謝礼の額もこの時点で確認しておく必要があります。
9.火葬場の手配
火葬場の予約もこの段階で行います。葬儀社が手続きを行ってくれる場合もありますが、自分たちで確認することも大切です。
10. 霊柩車とマイクロバスの手配
故人を霊柩車で運ぶ際の手配も重要です。霊柩車の種類やデザインを選ぶことができるため、故人のイメージに合ったものを選びましょう。また、会葬者の移動手段として、マイクロバスの手配も考慮します。多くの方が参加される場合、移動がスムーズに行えるように手配しておくことが大切です。
11.訃報通知
故人の訃報を周知するための準備を行います。親族や友人、知人へ連絡を取り、必要に応じて訃報のハガキやメールを送信します。
12.祭壇と位牌
祭壇の設置や位牌の準備を行います。生花や白木を使った祭壇の選択肢を検討し、故人を偲ぶための美しい空間を作ります。
13. 遺影写真
故人の遺影写真を探します。故人の好きな表情や思い出深い写真を選ぶことで、葬儀に参加する方々にも故人の人生を感じていただけるでしょう。
14.死亡届の手続き
家族または葬儀社が役所で死亡届を提出する手続きを行います。この手続きは法律上の義務であり、しっかりと行うことが必要です。
15. 通夜振る舞いの食事
通夜を行う場合、会葬者に対して振る舞う食事の手配を考えます。故人を偲ぶ場での食事は、参加者にとって大切な時間となりますので、心を込めた準備を行います。
16. 会葬礼状と会葬返礼品
会葬礼状は、葬儀に参加してくださった方へ感謝の気持ちを伝えるために重要です。また、会葬返礼品も準備し、故人を偲ぶ際の記念としてお渡しします。
17.供花
故人を偲ぶための供花の手配を行います。家族や友人、知人からの供花を受け取ることで、故人への愛情を表現することができます。供花を受けるかどうかも喪主が決める必要があります。
18.精進落とし
精進落としの食事の準備も考慮します。葬儀後には、喪主や近親者が集まり、故人を偲ぶ食事を共にします。この時間は、心の整理をする大切な場となります。
19.メモリアルな演出
故人を偲ぶためのメモリアルな演出を考えます。例えば、写真や映像を使ったスライドショー、故人の好きな音楽を流すなど、個性的な演出が心に残る葬儀を作り出します。
20. 喪主挨拶
会葬者に向けての挨拶を用意します。喪主としての挨拶は、故人への感謝の気持ちや、参加してくださった方々へのお礼を伝える重要な機会です。心のこもった言葉を準備しましょう。
3.女性が喪主を務める場合、
特に注意すべきスタイルや持ち物があります。
1.服装
喪主としての服装は、一般的には黒い喪服が望ましいです。和装(黒留袖)や洋装(ブラックフォーマル)を選ぶことができます。装飾は控えめにし、シンプルで落ち着いたデザインを選ぶことが重要です。アクセサリーも黒やシルバー系で統一すると良いでしょう。
2.持ち物
喪主として必要な持ち物には、以下のようなものがあります
喪服:事前にクリーニングを済ませておくこと。
数珠:仏式の場合、数珠は必需品です。持参しておくと安心です。
ハンカチ:涙を拭いたり、急な場面での準備として。
メモ帳:葬儀の進行や連絡先を書き留めるための備え。
お金:お寺へのお布施やお車代は布施袋やお車代袋にそれぞれ入れ、
袱紗で包んで用意しましょう。
また当日の急な出費に備えて少し多めに持参すると良いでしょう。
3.心構え
喪主としての心構えも重要です。故人を偲び、参列者に感謝の気持ちを伝えるための言葉を準備し、落ち着いて対応できるよう心掛けましょう。
以上のポイントを整理し、事前にしっかりと相談することで、喪主としての役割を果たしやすくなります。このように準備を進めることで、心の安定を保ちながら、大切な人を見送るための準備を整えることができるでしょう。大切な人をしっかりと見送るために、準備を進めていきましょう。
祈り百貨店では、葬儀に必要な必需品である数珠(念珠)も取り扱っております。いざという時に慌てないよう、事前に準備しておくことをおすすめします。
最近では、女性向けに色とりどりの美しい石や房を使ったものもあり、初めて購入される方はもちろん、以前「必要に迫られて選ばれた」方も、この機会に、じっくりと多様な種類の中から、ご自身の心により馴染む一品を見つけてみてはいかがでしょうか
年齢を重ねるごとに使用する機会が増えてくるかもしれませんので、よりお好みに合ったものにお買い替えいただくのもおすすめです。また、ご家族へのプレゼントにも最適です。
念珠の一覧はこちらから↓

シェア: